| 年代 | 花蹊 | 教育・研究 | 文芸 | 文化・風俗 | 政治 | 経済 | 国際 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840年 天保11年 |
跡見花蹊滝野、摂津国西成郡木津村に出生(4/9)。[0] | |||||||
| 1851年 嘉永4年 |
円山派画家石垣東山に入門。[11] | |||||||
| 1853年 嘉永6年 |
[13] | ペリー浦賀来航(6/3)。プチャーチン長崎来航(7/17)。 | ||||||
| 1854年 安政元年 |
[14] | 日米和親条約(3/3)。 | ||||||
| 1856年 安政3年 |
宮原節庵に漢学・詩文・書道を、円山応立・中島来章、南画の日根対山に絵画を学ぶ。寄寓先は伯父三宅勘左衛門。[16] | 蕃書調所 | ||||||
| 1858年 安政5年 |
大坂中之島に私塾。[18] | |||||||
| 1859年 安政6年 |
父、姉小路家に仕える。花蹊、塾経営。[19] | |||||||
| 1865年 慶應元年 |
大坂塾閉鎖。姉小路家へ。[25] | |||||||
| 1867年 慶應3年 |
不言亭。[27] | 王政復古(12/9) | ||||||
| 1870年 明治3年 |
京都私塾閉鎖し東上(11/17)。[30] | 大学規則・中小学規則。ミス・キッダー、英学塾(フェリス女学校前身)。ジュリア・カロゾルス、築地居留地にA六番⼥学校(キリスト教主義、女子学院前身) | ||||||
| 1871年 明治4年 |
[31] | 津田梅子留学。 | ||||||
| 1872年 明治5年 |
[32] | 竹橋に官立女学校(東京女学校)(お茶の水女子大学付属中学・高等学校の源流)。京都府、新英学校(女学校)、女紅場(女子手芸教授)。開拓使仮学校(札幌農学校前身)。東京師範学校。学制頒布(9/5)。 | 太陽暦(12月3日→元旦) | |||||
| 1873年 明治6年 |
女教院権訓導(5/13)。[33] | 東京外国語学校 | ||||||
| 1874年 明治7年 |
神田猿楽町13番地で試業〔開校記念祭〕(11/25)。[34] | 東京開成学校・東京医学校(5/7)。 | ||||||
| 1875年 明治8年 |
跡見学校、開校式(1/8)。女教院権訓導職辞す(1/31)。私学開業願(11/13東京府宛)。始業式(11/26)。[35] | 小石川植物園(2/27)。商法講習所(8東京高等商業学校前進)。札幌学校(9/7札幌農学校76/8/14)。東京女子師範学校(11/29)。同志社英学校(11/29)。 | ||||||
| 1877年 明治10年 |
[37] | 東京女学校廃校。東京大学(4/12)。華族学校(10/17学習院)。 | ||||||
| 1878年 明治11年 |
清国公使館に招待さる。[38] | |||||||
| 1879年 明治12年 |
[39] | 教育令 | ||||||
| 1881年 明治14年 |
[41] | 明治法律学校(明治大学前身)。東京職工学校(東京工業大学前身)。 | ||||||
| 1882年 明治15年 |
[42] | 上野博物館・上野動物園(3/20)。東京専門学校(早稲田大学前身)。下田学校。 | ||||||
| 1883年 明治16年 |
学校開申書(7/14)。[43] | 東京英和学校(東京英学校を改称、青山学院前身) | ||||||
| 1884年 明治17年 |
英語教育開始。米人ワッソン婦人。[44] | 学習院、宮内庁直轄校に。 | 英国博覧会(フィラデルフィア) | |||||
| 1885年 明治18年 |
[45] | 華族女学校(9/5)。天台宗大学(大正大学前身)。 | 宮原節庵没(10/6 80)。 | |||||
| 1886年 明治19年 |
[46] | 古義真言宗大学林(高野山大学前身)。帝国大学令。共立女子職業学校(3/11那珂通世ら、共立女子学園前身)。師範学校令。高等師範学校、学年開始を4月1日に。 | ||||||
| 1887年 明治20年 |
小石川柳町校舎建築着工(8/9)。[47] | 明治学院。哲学館(東洋大学前身)。 | ||||||
| 1888年 明治21年 |
小石川柳町移転(1)。『晃山記遊』。[48] | 工手学校(工学院大学前身)。東京天文台。 | ||||||
| 1889年 明治22年 |
父重敬没(81)。[49] | 私立和仏法律学校(法政大学前身)。日本法律学校(日本大学前身)。 | 大日本帝国憲法・皇室典範発布(2/11)。 | |||||
| 1890年 明治23年 |
初の卒業式(4/6)。私立跡見女学校規則改正(4)。[50] | 慶應義塾大学部。女子高等師範学校。東京工業学校。皇典講究所、国学院(国学院大学前身)。教育勅語(10/30)。 | ||||||
| 1891年 明治24年 |
[51] | 私立東京農業学校(東京農業大学前身)。孤女学院(滝野川学園前身)。中学校令改正(12):高等女学校の規定(初)。(私立学校撲滅論) | 東京ニコライ堂。 | |||||
| 1892年 明治25年 |
シカゴ博覧会「四季草花之図」出品(12/16)。[52] | |||||||
| 1893年 明治26年 |
[53] | 日本基督教婦人矯風会。 | ||||||
| 1894年 明治27年 |
跡見女学校規則改正、本科、予科の4年制。英学全廃(3/16サンマースら解雇)。[54] | 青山学院。 | ||||||
| 1895年 明治28年 |
[55] | 高等女学校規程(1/29) | ||||||
| 1897年 明治30年 |
[57] | 京都帝国大学。東京帝国大学。師範教育令。 | 博文館印刷工場(京橋区竹川町) | |||||
| 1898年 明治31年 |
物理科導入。[58] | 日本美術院。 | 帝国婦人協会 | 合資会社博進社印刷工場(小石川区久堅町) | ||||
| 1899年 明治32年 |
黒木綿五つ紋付式服。[59] | 高等女学校令(2)(「良妻賢母」主義)。私立学校令(8/3)。実践女学校。女子工芸学校。 | ||||||
| 1900年 明治33年 |
家政学、家政簿記導入(4)。本科(国語、漢文、数学、習字、裁縫、地理、歴史、家政、理科、唱歌)、予科(作文、算術、物理、地理、歴史、習字、書取、裁縫)、別科(絵画、英語、琴曲、点茶、挿花)の教育課程(5)。校舎増築(8)。『汲泉』発刊(6/10)。[60] | 京都法政学校(立命館大学前身)。帝室博物館。台湾協会学校(拓殖大学前身)。女子英学塾(津田梅子)。女子美術学校。東京女医学校。 | ||||||
| 1901年 明治34年 |
随意科的制度の廃止、本科、予科、選科、別科を置く。[61] | 高等女学校令施行規則(3)。日本女子大学校。 | ||||||
| 1902年 明治35年 |
本科(国語、漢文、数学、英語(随意)、習字、絵画、裁縫、地理、歴史、理科、家政、唱歌、体操)、別科(琴曲、点茶、挿花)の5年制教育課程。[62] | 早稲田大学。哲学館事件(12/13)。 | ||||||
| 1903年 明治36年 |
1年の補習科(割烹、礼法、簿記、英語、習字、絵画、裁縫等)の教育課程。[63] | 専門学校令。東京慈恵医院医学専門学校。東京法学院大学。明治大学。法政大学。哲学館大学。浄土宗高等学院。関西法律学校。専修学校。明治学院神学部。 | 日本基督教青年会同盟(Y・M・C・A)。 | |||||
| 1904年 明治37年 |
[64] | 慶應義塾大学部。青山学院高等科。台湾協会専門学校。日本女子大学。東北学院専門科。青山学院神学部。同志社専門学校。曹洞宗大学林。同志社神学校。大阪三一神学校。女子英和塾。日本大学。真言勧学院高等科。大阪高等商業学校高等科。青山女学院英文専門科。天台宗東部大学。早稲田大学。日蓮宗大学林。国学院。真宗大学。東京三一神学校。 | ||||||
| 1905年 明治38年 |
[65] | 古義真言宗聯合高等中学。仏教大学(竜谷大学前身)。中央大学(東京法学院大学改称)。東洋殖民学校。 | 『婦人画報』創刊(国木田独歩) | 日本基督教青年会同盟(Y・W・C・A)。 | 博文館印刷所。 | |||
| 1906年 明治39年 |
高等女学校令準拠5年制教育課程に改正。校舎改築(9)。[66] | 華族女学校を学習院に合併。国学院大学。東洋大学(哲学館大学改称)。帝国学士院(東京学士会院改組)。東京三一神学校。東京専修学校。 | ||||||
| 1907年 明治40年 |
[67] | 宗教大学(浄土宗大学改称)。日蓮宗大学(日蓮宗大学林改称)。師範学校規定。東北帝国大学。明治専門学校。立教学院立教大学。東京歯科医学専門学校。第1回文部省美術展覧会(文展)。 | ||||||
| 1908年 明治41年 |
[68] | 臨時仮名遣調査委員会(5森鷗外も委員)。高等女学校令改正(7)入学資格12歳以上の尋常小学校卒業者。奈良女子高等師範学校。東京女子高等師範学校(女子高等師範学校改称)。 | 田山花袋「一兵卒」(1)。夏目漱石『坑夫』(1連載開始)『夢十夜』(7連載開始)『三四郎』(9連載開始)。島崎藤村『春』(4連載開始)。永井荷風『アメリカ物語』(8)。徳田秋声『新所帯』(10連載開始) | 平塚明子、森田草平の塩原情死行(3)。 | ||||
| 1909年 明治42年 |
古希祝賀会(5/9)、来賓総代渋沢栄一。[69] | 東洋殖民学校廃止。帝国女子専門学校。真言宗聯合高野大学(高野山大学前身)。富山県立薬学専門学校。日本歯科医学専門学校。神戸女学院専門部。 | 森田草平『煤煙』(1連載開始)。北原白秋『邪宗門』(3)。永井荷風『ふらんす物語』(3発禁)「すみだ川」(12)。夏目漱石『それから』(6連載開始)。森林太郎「ヰタ・セクスアリス」(7発禁)。田山花袋『田舎教師』(10)。二葉亭四迷死去。レーニン『唯物論と経験批判論』。 | 大日本精糖贈収賄事件(4)。東京高商学生同盟総退校決議(5/11)。伊藤博文暗殺(10)。 | ||||
| 1910年 明治43年 |
大和田建樹没(54)。[70] | 高等女学校令改正(10)「実科」の規定。家政教育機関。九州帝国大学。 | 島崎藤村「家」(1連載開始)。森鷗外「青年」(3連載開始)「普請中」(6)「沈黙の塔」(11)。夏目漱石「門」(3連載開始)。長塚節「土」(6連載開始)。谷崎潤一郎「刺青」(11)。石川啄木『一握の砂』(12) | 幸徳秋水ら逮捕・大逆事件(6) | 日韓条約(8韓国併合)、朝鮮総督府。 | ハレー彗星出現(5) | ||
| 1911年 明治44年 |
[71] | 南朝正閏通達(2/27)。文部省文芸委員会(5森鷗外、上田敏、幸田露伴、島村抱月)。東京神学社神学専門学校、東京女子神学専門学校。聖公会神学校(聖教社神学校改称)。臨済宗大学(花園学院高等部改称)。真宗大谷大学(真宗大学改称)。東京農業大学(東京高等農学校改称) | 平塚らいてう『青鞜』(9)。森鷗外『雁』(9開始)。谷崎潤一郎『刺青』(12)。 | カフェ・プランタン、ライオン、パウリスタ開業。吉原大火(4)。イルミネーション、蓄音機普及。 | 大逆事件大審院判決(1)。片山潛、社会党。 | 辛亥革命 | ||
| 1912年 明治45年・大正元年 |
勲6等宝冠章(7/8)。[72] | 日本武徳会武術専門学校。同志社大学(同志社専門学校改称)。同志社女学校専門部。関西学院(関西学院神学校改称)。東京女子医学専門学校。高千穂高等商業学校。高等学院。日本医学専門学校。真宗学院。 | 森鷗外「かのやうに」(「僕の思想が危険思想でもなんでもないと云ふことを」)(1)「興津弥五右衛門の遺書」(10)。夏目漱石「彼岸過迄」(1連載開始)「行人」(12連載開始)。美濃部達吉『憲法講話』。石川啄木没。 | 団子坂菊人形終了。第5回オリンピック・ストックホルム大会。 | 明治天皇崩御(7/30)。 | |||
| 1913年 大正2年 |
財団法人跡見女学校設立認可(11/21)。[73] | 上智大学。仏教専門学校(高等学院改称)。教育調査会(文部省諮問機関)。専修大学(専修学校改称)。立命館大学(京都法政大学改称)。東北帝国大学理科大学に女子3名入学。 | 森鷗外『阿部一族』(1)。平塚らいてう「私は新しい女である」(1)。島崎藤村渡仏(4)。斎藤茂吉『赤光』(10)。 | |||||
| 1914年 大正3年 |
[74] | 私立大学智山勧学院。真言宗聯合大学(真言宗聯合京都大学改称)。 | 森鷗外『堺事件』(1)。阿部次郎『三太郎の日記』(4)。島崎藤村『桜の実の熟する時』(5)。高村光太郎『道程』(10) | 第1次世界大戦(7) | ||||
| 1915年 大正4年 |
「行儀作法の心得」(生徒配布)。『をりをり草』(実業之日本社)(10/10)。校服制定(11/15)、紫紺木綿・紫袴。[75] | 青山学院神学部・高等学部(青山学院神学科・高等学科改称)。東京学院高等部(東京学院高等科改称)。聖心女子学院高等専門学校。 | 森林太郎『山椒大夫』(1)『最後の一句』(10)。徳田秋声『あらくれ』(1連載開始)。夏目漱石『道草』(6連載開始)。有島武郎『宣言』(7連載開始)。芥川龍之介『羅生門』(11)。 | 武蔵野鉄道(4) | 対華21ヶ条要求(1) | |||
| 1916年 大正5年 |
喜寿祝賀(5/8)。[76] | 真言宗高野山大学(真言宗聯合高野大学改称)。伝染病研究所、東京帝国大学付置に改組。日本ルーテル神学専門学校。成蹊実業専門学校。 | 森林太郎『高瀬舟』(1)『渋江抽斎』(1連載開始)『伊沢蘭件』(6連載開始)。芥川龍之介『鼻』(2)。『青鞜』終刊(2)。夏目漱石『明暗』(5連載開始)。島崎藤村帰国(7)。永井荷風『腕くらべ』(8)。中条百合子『貧しき人々の群』(9)。芥川龍之介『芋粥』(9)。倉田百三『出家とその弟子』(11)。夏目漱石没(12) | 婦人の洋装。 | 吉野作蔵「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの道を論ず」(1)。 | |||
| 1917年 大正6年 |
『婦人世界』講演会(4/28)。『女の道』(泰山房)。跡見重威没(76)。[77] | 森鷗外、帝室博物館長兼図書頭。真言宗京都大学(真言宗聯合大学改称)。理化学研究所。成城小学校。早稲田大学学校騒動(8/22)。モリソン文庫。拓殖大学(東洋協会殖民専門学校改称)。 | 萩原朔太郎『月に吠える』(2)。河上肇『貧乏物語』(3)。志賀直哉『城の崎にて』(5)『和解』(10)。芥川龍之介『羅生門』(5)。有島武郎『惜しみなく愛は奪う』(7)。『カインの末裔』(7)。芥川龍之介『戯作三昧』(10連載開始)。 | ロシア二月革命、十月革命。 | ||||
| 1918年 大正7年 |
専門学校入学者検定規定による指定(9/2)。髪型ガバレット採用(11/18)。[78] | 帝国殖民学校閉鎖。東京女子大学。北海道帝国大学。東京医学専門学校。東京女子神学専門学校廃止。女子学習院(学習院女学部独立)。神学社神学校(東京神学社神学専門学校改称)。北里研究所。大学令・高等学校令(12)。 | 有島武郎『小さきものへ』(1)『生まれ出づる悩み』(3連載開始)。島崎藤村『新生』(5連載開始)。芥川龍之介『地獄変』(5)『蜘蛛の絲』(7)『奉教人の死』(9)。『赤い鳥』創刊(7)。武者小路実篤『新しき村の生活』(8)。佐藤春夫『田園の憂鬱』(9)。和辻哲郎『古寺巡礼』(8連載開始)。津田左右吉『文学に現はれたるわが国民思想の研究』(10)。 | 米騒動(8)。原敬内閣(9)。新人会(12)。 | ||||
| 1919年 大正8年 |
校長辞任(3/31)。藤井瑞枝編『跡見花蹊先生実伝 花の下みち』(5)。[79] | 帝国大学令改正(2/7)。神戸女学院大学部(神戸女学院専門部)。活水女子専門学校。京都薬学専門学校。高等学校学年始期4月1日に改正(前9月11日、3/29)。帝国美術院、帝展。大倉高等商業学校。 | 菊池寛『恩讐の彼方に』(1)。有島武郎『或る女』(3,6)。幸田露伴『運命』(4)。津田左右吉『古事記及び日本書紀の新研究』(8)。武者小路実篤『友情』(10)。 | 大日本労働総同盟友愛会(8)。 | コミンテルン(3)。五・四運動。ヴェルサイユ条約(6)。 | |||
| 1920年 大正9年 |
[80] | 慶應義塾大学。早稲田大学。東京帝国大学に女子入学(9/24)。東京商科大学(東京高等商業学校)。法政大学。明治大学。中央大学。日本大学。國學院大学。同志社大学。高等女学校令改正。 | 新婦人協会(3/28平塚雷鳥・市川房枝ら)。 | 森戸事件(1/13)。 | ||||
| 1921年 大正10年 |
教員会で、名誉校長の主義方針を開陳(国体尊重へのよき指導・改善への意見開陳を希望)。[81] | 西南学院高等学部。自由学園。文部省「思想善導」内訓(8/27)。京都府立医科大学。東京慈恵会医科大学。明華女子歯科医学専門学校。 | 『種蒔く人』 | 原敬暗殺事件。裕仁親王摂政宮(11)。 | ||||
| 1922年 大正11年 |
[82] | 東京裁縫女学校専門部。梅花女子専門学校。常用漢字。熊本医科大学。龍谷大学。大谷大学。専修大学。立教大学。立命館大学。関西大学。東洋協会大学。 | 文部科学省『学制五十年史』。 | ワシントン会議 | ||||
| 1923年 大正12年 |
[83] | 大東文化学院専門学校。 | 関東大震災(9/1)。 | |||||
| 1924年 大正13年 |
埼玉県白子村の土地受贈(1/16)。[84] | 明星学園。男子学校軍事教練開始。東洋文庫(モリソン文庫改組)。 | メートル法実施(7/1)。 | |||||
| 1925年 大正14年 |
勲5等瑞宝章(4/25)。[85] | 帝国婦人協会実践女学校専門学部。帝国女子医学専門学校。共立女子職業専門学校専門学部。駒沢大学。樟蔭女子専門学校。 | ラジオ放送開始 | 共同印刷株式会社創立(博文館・精美堂合併)。普通選挙法。治安維持法。全国女子学生同盟(4/17)。京都学連事件(12/1)。 | ||||
| 1926年 大正15年・昭和元年 |
花蹊没(1/10)。遺作集『花のしづく』(12)。 | 日本医科大学。日本女子体育専門学校。高野山大学。大正大学。学生の社会科学研究禁止通達通(5/29文部省)。拓殖大学(東洋協会大学改称)。 | 文芸家協会。 | 共同印刷ストライキ(1~3)。大正天皇崩御(12/25)。 | 日ソ基本条約 | |||
| 1927年 昭和2年 |
横光利一「春は馬車に乗って」(1)。芥川龍之介「河童」(3)「文芸的な、余りに文芸的な」(4連載開始)、自殺(7)、「或阿呆の一生」「歯車」(10)「侏儒の言葉」(「危険思想とは常識を実行に移そうとする思想である。」)(12)。川端康成『伊豆の踊子』(3)。佐藤紅緑「ああ玉杯に花うけて」(5連載開始)。平林たい子『施療室にて』(9)。 | |||||||
| 1930年 昭和5年 |
陸軍兵器廠跡地購入(6/12 大塚)。 | |||||||
| 1932年 昭和7年 |
『女の道』(朝日出版)。新校舎移転(12/19)。 | |||||||
| 1941年 昭和16年 |
『女の道』(内外出版社) | |||||||
| 1944年 昭和19年 |
跡見女学校廃止、跡見高等女学校(4/1)。 | |||||||
参考文献
- 高橋勝介『跡見花蹊女史伝』、東京出版社、1932年。
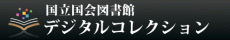
- 『跡見花蹊教育詞藻』中野一夫編、学校法人跡見学園、1995年。
- 『跡見学園年表』、学校法人跡見学園、中央公論事業出版、1995年。
- 一三〇年史編集委員会『跡見学園—一三〇年の伝統と創造』、学校法人跡見学園、2005年。
- 年表の会(石崎等他)『近代文学年表』(増補版)、双文社出版、4版1刷、2014年。
- 文部科学省サイト『学制百年史』「二 高等女学校令の制定」。
- 女子学院のサイト「女子学院の沿革」。
- お茶の水女子大学サイト「大学の沿革」。
- お茶の水女子大学サイト「オチャノミズ ジョシ ダイガク ヒャクネンシ」「オチャノミズ ジョシ ダイガク ヒャクネンシ」。
- 実践女子大学・実践女子大学短期大学部サイト「建学の精神と教育理念」。
- 共同印刷株式会社サイト「沿革」
- Wikipedia「危険思想」
- コトバンク精選版 日本国語大辞典「危険思想」